内容のー部もしくは全部が変更されてる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

- ©2017 Twentieth Century Fox
娘を殺された母親が警察を非難する文言をデカデカと看板に掲げる。それがピタゴラ装置のスタートだ。わずかにビー玉をスタートさせた一歩に過ぎない。それがあっちにぶつかり、こっちで跳ね返り、時に別のボールにバトンタッチしたりしながら思わぬところに着地する。
この母は完全に狂っている。娘の事件が彼女を狂わせたのかと言えばどうやらそうでもなく、もっと前から片鱗はあったようだ。冒頭こそ同情するが、すぐに行き過ぎだと感じる。
「警察なにやってんだ」というのは、私やもしかしたらあなたも、一度ぐらい口にしたことがあるかもしれない。当事者としての怒りが後押しすれば彼女と同じような行動に出ないとも限らない。看板を掲げないまでもSNSに投稿したりはするかもしれない。そして片田舎の看板よりもSNSの方がはるかに破壊力がある。鉄球でピタゴラ装置をやるようなものだ。
この作品は狂気を引き金にしたピタゴラ装置だ。大切なのは結末だけではない。そこへ至る過程で何が起こるのか。ゆっくりスタートしたビー玉が途中で辞書を倒したりする。そこに意外な展開など必要ない。単純な因果の連鎖だけで気づいたらとんでもないところにいるのだ。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
これは異様な映画だ。娘を殺害された母親という悲劇の人が主人公だ。しかし彼女の悲劇に同情できるのは最初の数分だけだ。一向に進展しない捜査に業を煮やして警察に文句の一つも言いたくなる。あるある。そこで警察なにやってんだと声高に言う。あるある。遺体発見現場の近くに巨大な看板を借りて警察なにやってんだと糾弾する。あるあ…る?大目に見てもここまでだろう。その後この母親はどっちが犯罪者かわからないような行為をしまくり、ついには火炎瓶で警察署を焼き払う。堂々と重犯罪者だ。
途中、回想シーンとして娘と言い合いをするシーンがある。どうやら母はそのことを悔やんでいるらしいことがわかるが、そもそもその言い合いのシーンで母に同情の余地はない。娘を殺されたことがきっかけなのではなく、彼女はもともと狂気の際にいたのだということが伺える。
この母の人物像は、まったく観客の同情を誘おうとはしていない。彼女に感情移入する映画ではないのだ。主人公に感情移入を拒否されたあたりで一歩引いて俯瞰するような形になる。すると描かれているのは因果の連鎖であることがわかる。一つ一つの要素を個別に取り出せば小さなことで、十分ありそうなことだ。それが一続きになることでとんでもないところへ連れていかれる。カオス理論のバタフライエフェクトのようだ。
ラストもなかなか印象的だ。もちろん、冒頭からは想像もつかないようなところを物語は走っている。結末を見せない幕切れになっているのがさらに良い。ピタゴラ装置は最後に旗を立てる直前までしか見られない。果たして旗は立ったのか。それとも踏みとどまったのか。イカレた母親は少々虚しさに気づき始めたようにも見えるが、それを否定する要素も散りばめられている。そしてすべては観客にゆだねられる。映画を見てあれこれ考えたい人には大いにお勧めしたい作品である。

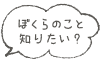





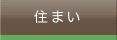
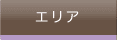
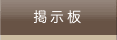


 早乙女カナコの場合は
早乙女カナコの場合は  名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN
名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN  キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド
キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド  ショウタイムセブン
ショウタイムセブン  室町無頼
室町無頼 












