内容のー部もしくは全部が変更されてる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

- ©2018「北の桜守」製作委員会
「北の〜」三部作最終章、というような言われ方をしているものの、三作の物語に関連はなくそれぞれ独立した作品だ。
本作は終戦間際に樺太から北海道へ引き揚げた母子を描いた物語である。1970年代に入り、子のほうは高度成長の目まぐるしい時代をまさに走っている。そんな折に十五年ぶりの再会をする母子。回想を挟みながら二人の生きた道を振り返るような作りになっている。酷い時代を懸命に生き抜いた。文字通りいろいろなことがあった。それを振り返りながら母子の絆、周囲の人との絆などを描く。
しかし。唐突に挟まる突飛な演出のパートは目に楽しいものの感情移入を大きく阻害する。もちろんそれを狙っているのだろうけれど、あまり心地よいものではない。また、母子の子のほうは今で言うとけっこうブラックなことを言う社長だ。彼をこういう人物にしたことがちゃんと回収されない。彼が母との交流で変化して良い社長になる、といった要素はなく、単に業績は上げていることがにおわされる。あちこちにばらまいた伏線はどれも回収が雑で、そんな風にしか出さないのであれば不要では、と思う部分も多々ある。感動はある。されど細部は気になる。そんな作品であった。(映画ライター・ケン坊)
ディノスシネマズ旭川、イオンシネマ旭川駅前、シネプレックス旭川で上映中
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
吉永小百合出演120作目。もちろん豪華な俳優陣が集った。それだけで価値がある。
冒頭からかなり意欲的な演出がされる。なるほどこういう方向の作品か、と思う。全編にわたり、何度か舞台演出が挟まる。その最初の一回目が入ったとき、「お。」という新鮮な驚きがある。印象的なシーンで効果的に使われる。ところがその後の挟まり方に規則性が無い。どういうシーンでこの舞台演出を入れるのか、入れないのか、という基準がよくわからない。そこに入れるのならこっちはなぜ、と思う部分がいくつかあり、そういう本筋と関係ない部分が引っかかってどうも物語に入り込めない。
特に気になるのは、母子の子の方、修二郎の描き方だ。優秀な兄に憧れと負い目を感じていた少年。それが苦難を乗り越えて地位を築いていく。成功者ではあるものの少々肩肘張りすぎな人物として登場する。そんな仕事第一で少々暴走気味に走っている彼が、十五年ぶりに母と再会し、道内各所の思い出の土地を巡る旅をする。その間仕事はほったらかしになる。社長不在の間に行われるオーナーの視察。社員たちが社長には見せない姿などが描かれる。社長の方も、母を最優先し、「そんなことをしていると社長を下ろされる」という指摘にも「それは覚悟の上だ」というようなことを言う。それなのに。それなのにである。この母との時間の果てに結局彼はどんな風に変化したのか。その変化が彼の仕事に、部下に、どんな変化をもたらしたのか。そうしたことは一切描かれない。それを描かないのなら彼が不在の間の店の様子をなぜ見せたのか。変化を見せないのならなぜ彼の暴走気味な一面をこれ見よがしに描くのか。こうした回収されない伏線がいくつもあり、見終えたあともすっきりしない。
母はただひたすらに悲しく、美しい。桜の思い出を大切に生きる。しかし母子の物語を楽しんで感動するという見方を作品が許してくれない。何を意図してこんな風になっているのか、ということを考えるのは一つの楽しみ方ではある。ただ、個人的にはこの作品ではそういう要素よりももっとシンプルに物語を楽しみたかった。

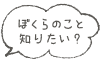

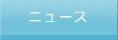



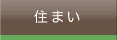
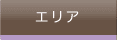
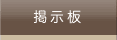
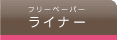


 ズートピア2
ズートピア2  TOKYOタクシー
TOKYOタクシー  プレデター:バッドランド
プレデター:バッドランド  死霊館 最後の儀式
死霊館 最後の儀式  秒速5センチメートル
秒速5センチメートル 












