内容のー部もしくは全部が変更されてる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

- ⓒ2019「天気の子」製作委員会
北海道にいると感じないけれど、ここ数年、それまで見たことのない自然現象が頻発するようになった。ゲリラ豪雨。文字通りバケツの底が抜けたような大量の雨が短時間に、狭い範囲に降る。局所的に冠水するほどの大雨が唐突に前触れもなく降る。ゲリラとはよく言ったものだ。私は雨が好きなのであまり苦にならないけれど、やはり自分の都合で「あした天気になあれ」と思うことはある。日本には古来から天に雨を乞うという文化がある。小野小町が雨乞いの歌を詠んだら本当に雨が降ったといったような伝承もある。本作は雨乞いとは反対に、ゲリラ豪雨の頻度がどんどん増し、晴天が減って行く中で「晴れ」を乞うという形で巫女のようなことをする少女が登場する。日常のすぐ隣にある神秘。思えば新海監督はそういうモチーフを描き続けているような気もする。
本作の舞台は池袋〜代々木あたりで、緻密に描かれた町並みは訪れたことがあれば匂いまで漂ってきそうだ。なのにそこで動いているキャラクタからは不思議なほど匂いがしない。見終えるとさまざまな想いが去来する。無数の解釈があり得るだろう。見終えた後でゆっくり話をする。もう一度見たくなる。これはそんな映画だ。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
新海監督はこれまでも、ディテールを描きこんだ緻密な背景を使って町を、特に都会、とりわけ東京を描いてきた。リアリティあふれる東京は、訪れたことのある人が見れば実写みたいなリアルを感じるだろう。そしてそのリアリティあふれる背景を舞台に、リアリティのまったくない話を展開する。本作は日常的な部分と神秘的な部分のバランスが半々ぐらいなので、日常部分にはもう少しリアリティがあったほうが良かったのではないかと感じた。ごく当たり前の日常から僅かな膜一枚で隔てられた神々の領域。おそらくはそういうことなんじゃないだろうかと思いながら見たのだが、当たり前のはずの日常にありそうもないことが描かれているので、全体的に世界が曖昧に見える。もしかしたらそれこそが狙いなのかもしれない。しかし例によって池袋〜代々木あたりの町の描写は見事で、訪れたことがあれば匂いまで漂ってくるほど緻密に描かれている。町並みからは匂いがするのにそこで動いているキャラクタからは匂いがしない。どのキャラクタにも実在感がまったくないのだ。この匂う町と匂わない人というコントラストは新海作品の特徴かもしれない。
ごく普通の(よく考えると全然普通ではないのだけれど)個人が神々とつながってしまい、超人的な能力を身に着けてしまう。世界さえ変えてしまうようなその力をどのように使うのか。個人という最小単位が、家族、町、組織、国家などを飛び越えていきなり世界をどうこうするような話になるジャンルを総称してセカイ系と呼んだりするが、そういう意味で本作もセカイ系だ。そしてセカイ系の定形として、セカイを取るのか個人を取るのか、という究極の選択が突きつけられる。そのときあなたはどうするのか。奇しくも直近に公開されたトイ・ストーリー4で、これまで利他の心で動いてきたウッディが他より己を優先する決断をする。ウッディが天秤にかけたものはセカイほど巨大なものではなかったけれど、反対側に乗っていたものは自分だった。本作と似たような天秤としては、エヴァンゲリオンの旧劇場版がそうだろう。セカイがどうにかなって人類が補完されたとき、主人公は利己的な決断をする。本作はそれを彷彿とさせる展開だった。
中盤まではおよそ予想通りだ。自由に晴天を呼べる少女。その強大な力はもちろん、大きな代償を要求する。セカイと引き換えに自らを贄とする。まあそうだろう。そして残された主人公は思いを胸に生きて…いかない。もう一度彼女に会いたいという想いで行動し、本当に呼び戻してしまう。ここでああハッピーエンド、となると割と普通だが本作はそうならない。正常な天候と引き換えに自らを贄とした少女が、やっぱりやめたと言って戻ってくる。すると彼女の身柄と引き換えだった正常な天候は失われ、晴天は訪れなくなる。そして3年が過ぎた。度肝を抜かれた。『君の名は』でも中盤の急展開に度肝を抜かれたけれど、今回もまた驚かされる。雨が止まなくなった東京は水没した。「セカイはすっかり変わってしまった」というようなのんきなセリフで描写される。本当はそれどころではないはずだ。首都東京が水没し、日本は国家として機能しなくなる。上を下への大騒ぎになっているはずだし、極端な貧困が訪れたりするだろう。ところが本作はそうはならない。単に水没しただけなのだ。景色が変わっただけで生活は変わらない。水没した東京でこれまでと同じ人々が同じように暮らしている。水没したからマンションに引っ越した、という程度の話としてしか描かれない。そう。そこにリアリティは全くなく、リアリティを追おうとした気配すらない。
新海監督が描いているのはこれまでもずっと「背景」であった。人物よりも背景。思えば最初の作品、「彼女と彼女の猫」は緻密な背景と顔の出ない主人公、そして落書きみたいな猫が描かれていた。一貫してディテールを詰め込んだ背景を描き、そこに存在の見えないキャラクタを乗せるという作りになっているのだ。
この作品は見てもらえばわかるけれど、語るべきことがたくさんある。語りたいことがたくさんある。何をどう解釈するのか。可能性が無限にある。どのような解釈も可能だし、そこからどんなメッセージを感じるかも人によるだろう。大いに議論できるししたくなる。そしてもちろん、そういう映画は文句なしに「いい映画」と言えるのだ。

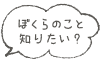





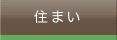
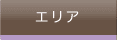
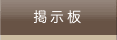



 早乙女カナコの場合は
早乙女カナコの場合は  名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN
名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN  キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド
キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド  ショウタイムセブン
ショウタイムセブン  室町無頼
室町無頼 












