内容のー部もしくは全部が変更されてる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

- ©2019「グッドバイ」フィルムパートナーズ
太宰治の遺作であり、未完で終わっている小説『グッド・バイ』。太宰版はタイトルに「・」が入る。本作はそれをケラリーノ・サンドロヴィッチが膨らませて舞台で上演されたものの映画化である。
映画は大泉洋と小池栄子によるコメディということで、その予想を裏切らない大笑い喜劇に仕上がっている。たくさんの愛人を抱える男が、本妻との生活に戻るため愛人たちと別れようとするというのが大筋の話で、原作は前述のように未完だが、太宰本人による「逆に本妻から別れを切り出されてしまう」という構想は残されていたようだ。本作はその部分を含めて原作に続きを付け足したものなのだが、特に後半の展開は想像を超えている。
序盤は大笑いのコメディで底抜けに面白いのだが、後半異質な展開になり始めたとたんに置き去り感があり、作品世界が急に遠いものになってしまう。終盤は予測不能の展開になるけれどあまり心地よい驚きではなく、「えぇ?そんな風になっちゃうの?」という感覚で笑いは急速にしぼんでしまう。
太宰がこの小説を書き終えずに自ら死を選んでしまったことが返す返すも残念だ。この映画は半ば逆説的な形でそれを思い起こさせる。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
たくさんの愛人と手を切るために偽装夫婦となる二人。「十人ちかく」もいるという愛人を偽物の妻を伴って訪問し、一人ずつ別れていこうとする物語。太宰治によるその原作は序盤も序盤、二人目の愛人を訪れようとするところで終わっている。周知のように太宰は、この作品を書き上げることなく入水自殺してしまった。十人ちかくいるはずの愛人がこのあと一人一人登場し、それぞれとそれぞれのやり取りがあるはずだっただろう。編集者には、しまいには自分の女房からグッドバイされてしまう、という構想が語られていたそうだ。偽物の妻を伴って愛人にグッドバイを持ちかけるうち、女房からグッドバイされてしまう。となれば、偽の妻といい感じになってそちらに落ち着く、といった展開は想像に難くない。舞台がしっかり用意された上、序盤で終わってしまっている太宰の『グッド・バイ』は、その後の展開をあれこれ妄想しやすい題材と言える。
本作はその妄想展開を形にしたもので、女房からグッドバイされる展開はなかなか興味深い。原作に登場する人物を巧みに使った展開で、いささか強引ではあるものの笑いを誘う形で着地する。しかしそのあとの展開がすごい。これはもういろいろな意味ですごい。特に謎の占い師が登場するあたりからの急展開は想像を超えている。唐突に登場する占い師は全知の神みたいな存在で、何もかも言い当てる。もはや占いではなく予言だ。そしてこの存在に関する説明が一切ない。現実味のない演出で物語に登場し、ストーリーの展開に対して巨大な役割を演じながら何も説明されない。この占い師の存在があまりにもご都合主義的で、一気に興がさめる。主人公の田島に対しての物言いもほとんど神のようで、これだけなら神の啓示みたいなものとして、実存ではないという解釈もできたのだが、その後清川という人物がこの占い師のおかげで宝くじを当てる、という展開が用意されたことでさらなるご都合主義が顔を出す。そして田島は暴漢に襲われ、死んだかに思われたが実は記憶を失って生きており、二年後に戻ってくる、という展開になる。この展開はもう荒唐無稽ともいうべきものだ。
太宰の原作をベースに喜劇として、上質な役者も相まって大変心地よいスタートを切るのに、中盤からの荒唐無稽がそれを台無しにする。荒唐無稽がドタバタ喜劇になっていればそれもそれで面白かったと思うのだがそうはなっていない。特に占い師からののくだりはライティングなどの演出も急にわざとらしくなり、安っぽいコントみたいになってしまう。この映画を見てあらためて太宰の原作を読んでみると、見事に、太宰の書いた部分が面白く、その後の付け足した部分はやはり付け足しに過ぎないという印象を強くする。太宰がこの作品を書き終えなかったことは返す返すも残念だ。

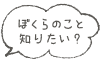





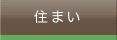
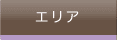
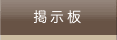


 早乙女カナコの場合は
早乙女カナコの場合は  名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN
名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN  キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド
キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド  ショウタイムセブン
ショウタイムセブン  室町無頼
室町無頼 












