内容のー部もしくは全部が変更されてる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

- ⓒ2022 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.
冒頭で発見される死体。ほどなく殺人の疑いで一人の女性が逮捕される。舞台は1969年のアメリカ。主人公は小さな町に隣接する湿地帯に一人で暮らしている風変りな人物だが、そうなるに至る経緯は悲惨で見ているのが辛い。しかし町の住民は彼女に同情するどころか差別する。手を差し伸べようとするのは黒人の夫婦二人だけだった。そんな中、町の実力者の息子が死体で発見され、主人公に嫌疑がかかる。町民はほとんどが被害者の味方だ。その町民たちが陪審員を務めるという圧倒的に不利な裁判が進行し、並行して彼女の半生が少しずつ明らかになる。自然の中で学校へも行かず、動植物に触れながら育ってきた女性。町の人々に蔑まれ、差別されることで人との交流も少なく、人よりも鳥や昆虫と接して暮らしている。そんな彼女は町という社会の中で異物となり、社会はその異物を許容しない。
この作品は殺人事件を追うサスペンスであり、裁判を描く法廷ものであり、主人公の恋愛を描いたラブストーリーでもある。そしてラスト10分、想像を超えた展開になり、言葉にしがたい後味と共にエンドロールを眺めることになる。ここには異物を許容しない社会の生む歪みの一端が描かれている。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
殺人事件の嫌疑をかけられた女性を描く作品だが、その女性が非常に特異な生き方をしている人であるという点に特徴がある。物語は事件の顛末を追うというよりは、彼女の半生を追うという体裁になっている。彼女の半生を描くことは古き悪しき差別的慣習を思い出させ、それが決して「古き」に留まらず、今もなお残っていることを思い起こさせる。1969年に起きた事件という舞台設定ではあるものの、ここで描かれる差別、排他思想等は今の社会においてもたびたび問題になるものと酷似している。多様性を叫ぶ裏に同時にこの排他性が見え隠れし、社会がある種の社会性を保ったままこの排他性を排除することはできないのではないかとさえ思う。
作中で弁護士が被告(主人公)に対し、「町の人々のことは嫌いかもしれないが」と言い、主人公が「嫌っているのは向こうであってわたしではない」と答えるシーンがある。これがあらゆる状況を物語っている。ある種の差別が排他主義を生み、特定の誰かを孤立させる。孤立したものは内へ閉じるしかなくなり、回復の見込みが消失する。小さな溝はやがて越えがたい断絶となり、復元しようのない歪みになる。この話は50年以上前の出来事として描かれているが、この排他性による歪みは現在の日本社会でもあちこちで見られる。クリーンな状態を保とうとすれば異物は排除するしかなくなり、排除された異物は消えてなくなるのではなく、見えないところに隠れるだけである。やがてくすぶっていた火種は爆発し、刃となって社会を破壊する。歴史から何も学ばない人々が今もなおクリーンを目指して異物を排除し続ける。
作中で裁判を描いているため、この裁判の決着が作品の結末かなと想像して見ることになる。しかし裁判の判決が下りたところで映画は終わらない。その後の物語はかなり圧縮された状態で駆け足に描かれる。主人公と心を通わせた男性との暮らしが描かれ、町の恩人の死が描かれ、最後は主人公の死までが描かれる。主人公は60代で死去し、夫が後に残される。残された夫が最後、裁判での無罪判決の決め手の一つであった、被疑者の自宅から見つからなかった死体から持ち去られたペンダントを彼女の日記の中から発見する。この事態は、主人公が実際は有罪であった、殺人を犯したことを示唆するもので、だとすると裁判の際に無罪の主張となったいくつもの状況は、逆に彼女が普通一般の人間には成し得ないほど冷酷に人を殺せる人であったことを物語る。
このラストシーンにより、映画の後味はがらりと違うものに変質する。悲劇的な境遇を生き抜いた彼女への同情、無罪になって良かったという気持ちがひっくり返る。ヒトという生き物の持つ社会性からはじき出された個体はヒトであることをやめ、野生動物の「生きるための知恵」を抵抗なく発揮するようになるのだ。そう思って本編を振り返ると数々の伏線が張られていたことに思い至る。社会という仕組みなしでは成立しないヒトという生き物は、もはや野生動物とは全く異なる動物になってしまっていることを思い知らされるのである。

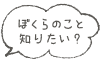

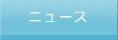



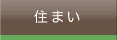
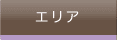
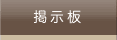
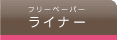
 クライム101
クライム101  ほどなく、お別れです
ほどなく、お別れです  クスノキの番人
クスノキの番人  ワーキングマン
ワーキングマン  シネマの時間2025 宇宙映画10選
シネマの時間2025 宇宙映画10選 












