
- ©Universal Pictures. All Rights Reserved.
ロバート・オッペンハイマーの半生を描く伝記映画であり、その時代を描く歴史映画でもある。ただ、時系列がシャッフルされているため、史実の順序を知らないと少々わかりにくい。映像の演出としてそれぞれの時間軸で色を変えてあり、人物の風貌もはっきりわかるような差がつけられてはいる。が、モノクロで表現されているシーンが時系列ではもっとも新しいなど、ノーラン監督らしい挑戦的な演出になっている。これによってお話の流れは各所で引っかかり、スムーズには流れない。特筆すべきは「音」。映像面でも前述のようにかなり引っかかりのある演出がされているのだが、音もそこに一役買っている。どちらかというと心地よくない音の表現がされ、ざらついた気分に押し込まれる。描かれている人物の心理、感情などが観客にも言葉を超えた次元で突きつけられる。この演出力はさすがノーランと思わされる。この「音」だけは映画館に行かないと体験できないので、ぜひ映画館で見てほしい作品である。
かくして人は禁断の、自らを滅ぼす力を手に入れた。力を手にしたものが次の望むのはさらなる力。果たして世界はその力の飽和に耐えることができるのだろうか。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
史実に基づいて描かれる伝記映画であるため、基本的にネタバレみたいなものは無い。特にこの作品は日本での公開がだいぶ遅くなったため、すでにどんな作品であるかの評判も聞こえてきていて、作品の重要な要素(実際の日本への原爆投下シーンは無い、など)は事前にわかっていた。
この作品は発表当初から、監督がクリストファー・ノーランであること、題材がロバート・オッペンハイマーであること、の二つの理由で注目していたし、見たいと思って楽しみにしていた。ところが公開当初、日本へのさまざまな意識(どちらかというと配慮なのか)から日本では公開されないことになり、今回公開されるまで複雑な思いで待つことになった。
この作品はタイトルの通り、ロバート・オッペンハイマーという人物の反省を描いた伝記映画である。
戦後、1947年にプリンストンの高等研究所の所長に任命されたオッペンハイマーは、その後1954年にいわゆるオッペンハイマー事件で公職から追放された。この追放劇の黒幕が彼を高等研の所長に任命したルイス・ストローズであり、そのストローズは1959年の公聴会で糾弾されることになった。本作で唯一モノクロで表現されているのがこのストローズの公聴会シーンで、作中の時系列ではここが最も新しい。モノクロだから古そうに見えるのだが、この時点が作中の「現在」であり、この「現在」は作品が作られた2023年から見るとだいぶ古いためモノクロで描かれているのだろう。本作はこの古い「現在」から過去を振り返り、回想として描いているため、回想シーンに色がついているという感覚である。
過去に『テネット』や『インセプション』で時系列をシャッフルして多様な解釈の余地を残した作品を作ってきたノーラン監督。本作は既に史実としてあるストーリーをシャッフルすることで観客の心理に訴えかけてくる。本紙でも書いたように音の演出も含め、作品全体がとても意欲的であると感じる。
ただ、どれほど意欲的に描いてあっても、核兵器を描いたどの映画もみな、日本人から見るとまったく「わかってない」ように見える。本作みたいな歴史作品以外にも、純粋なエンターテイメントアクションなどにもよく核兵器は登場するが、どれも「すごい爆弾」としてしか描かれていない。核の重要な点は「汚い」爆弾であることなのだが、おそらく日本で原爆資料館などを見ない限り、核兵器がどのように「汚い」のかわからないのだろう。本作の個人的な注目点はここだったのだが、この作品、この監督でもやはり核兵器は「すごい爆弾」としてしか描かれなかったことに些かの失望は覚えたが、同時にまあそんなものだろうという諦観もある。逆に言えばこの部分を表現できるのは日本人だけであり、日本からそれを作品として世界に問うていく必要があるのかもしれない。

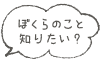





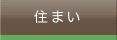
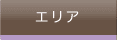
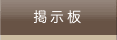



 早乙女カナコの場合は
早乙女カナコの場合は  名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN
名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN  キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド
キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド  ショウタイムセブン
ショウタイムセブン  室町無頼
室町無頼 












