
- ©2024「九十歳。何がめでたい」製作委員会
©佐藤愛子/小学館
なにもかもが奇跡みたいな映画だ。原作はあまりにも売れた佐藤愛子のベストセラーエッセイであり、著者は昨年100歳を迎えられてなお健在である。このエッセイをもとにして著者である佐藤愛子を描いた映画が本作なのだが、本作でその佐藤愛子を演じるのが草笛光子、御年90歳である。90歳の人物を90歳の俳優で映画化する。こんなことが実現したのはほとんど奇跡なのではないだろうか。
物語は脚色が大変良くできている。エッセイのタイトルを冠しているがエッセイの映画化ではなく、それを書いたときの佐藤愛子を描く伝記的なお話になっている。時代遅れのロートルと化した熱血編集マンが、さらに倍ほども年をとっている作家のもとへ仕事を依頼しに来る。二人の軽妙なやり取りには様々な人間模様が見え隠れし、それほど多くないエピソードから実に深い印象を残す。
御年90歳の草笛光子は元気だし張りがある。その元気の秘訣は声であろう。しっかり腹から声を出すというのが健康にもとても良いことが伺える。しっかり声を出してはっきりとものを言う。そうやって明日からも生きていこうと思えるような、元気、勇気、あるいは活力のようなものをくれる映画である。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
時代遅れ。この言葉は年を重ねていくものに必然のように突きつけられるもので、ある程度避けがたいであろう。しかし、時は令和となり、時代の流れがあまりにも早い。十年一昔と言われた時代があったけれど、今特にテクノロジーの分野では二週間前の技術がもう古い。このようなペースで時代が変化していく今、年齢に関係なく誰もが時代遅れになり得る。本作では主人公に後期高齢者(90歳)の作家を置き、彼女を担当する編集者に中年(おそらくアラフィフ)の熱血編集マンを配置している。化石みたいなレジェンドを時代遅れの編集マンが動かしてエッセイを連載し、のちにそれが単行本となる。この本が実際にリリースされたのはそれこそ十年一昔単位での一昔前であり、編集マンは本当に当時のロートルだったのかもしれないが、この時代は現在ほどコンプライアンス意識は高くなく、現在の感覚からすればふた昔ぐらい古いはずである。映画はそこを現在の感覚にアップデートしてあるため、ロートル編集マンは完全にアウトな人物として描かれている。
この辺が実際とどの程度違うのかがわからないのだが、こうして作られたこのエッセイは、実際に爆発的に売れた。
映画の中でも、実際のエッセイに書かれている内容が、草笛光子の朗読のような形で表現されている。90歳にもなるおばあさんが「昔はこうだった」などという話をしたところで、当然現在の感覚にはまったく合わない。にもかかわらず、これが老若男女を問わず共感を呼び、大ヒットしたのである。時代遅れとはいったいなんだろうか。
この映画には時代に合わなくなった価値観が数多く登場する。でもその中には、今から先の世界を生きるのに、知っていると楽しくなるようなものも、いくらか含まれていたように思う。元気の出る映画として、ときどき見返したい作品であった。

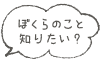





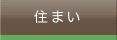
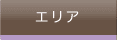
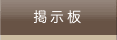



 早乙女カナコの場合は
早乙女カナコの場合は  名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN
名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN  キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド
キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド  ショウタイムセブン
ショウタイムセブン  室町無頼
室町無頼 












