
- ©2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
少女の心の中で様々な感情がせめぎあう様子を描いたアニメーション作品『インサイド・ヘッド』。本作はその二作目で、主人公の少女ライリーは13歳を迎える。ヨロコビたち感情が司っていたライリーの指令室に「思春期アラーム」が鳴り響き、改築工事が行われる。新たにより複雑な感情たちが現れ、ヨロコビたちは指令室から追い出されてしまう。
この作品は少女の成長を「感情」という側面から描いていくのだが、その展開が実に見事だ。新たな感情を制御できずに苦悩する少女の様子がとても瑞々しく描かれている。幼いころ自分を動かしていた純粋な感情、喜怒哀楽といったものたちがよそへ追いやられ、不安や嫉妬、羨望、虚栄、怠惰などが渦巻き、自己嫌悪に陥ったりする。精神的な葛藤は悪いことではなく、むしろ成長に不可欠だ。かといって制御不能の状態で良いわけでもなく、うまく折り合いをつける必要がある。
ヨロコビがたどり着いた答えはこれ以上ないものであった。成長するとはどういうことなのか。自分っていったいなんなのか。本作はこの難しいテーマを見事に描いている。自分の中の感情の指令室を想像すると、僕らも少し生きやすくなるかもしれない。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
前作に登場した感情たち。喜怒哀楽や恐怖心、苛立ちといったものは人にとってシンプルなもの。言い換えると根源的な、より本能に近いものであった。進化の過程で社会性を持つに至った人という種族には、この根源的なものからより複雑化した感情がある。しかしより複雑な感情は赤ちゃんの時から備わっているわけではなく、成長していく過程で獲得されていくものだ。本作はそれを実に見事に描いていて、驚くべき脚本だと思う。
赤ちゃんのとき、何の制御もかかっていないフリーダムな状態で感情は爆発し続けている。喜んだり悲しんだり怖がったり苛立ったり。一つ一つの感情は「純」なまま発露する。前作はその状態から成長し、感情をコントロールするに至る過程を描いていた。ヨロコビたち感情のキャラクタは、自分ばかりが主張するのではなく、時に怒ったり、悲しんだりすることも必要だと理解し、お互いが手を取り合ってライリーを操縦していけるようになった。そして、いやな気分になった記憶は記憶の彼方へと放り出し、「必要ないもの」として捨てることで気分よく過ごしていた。
本作は冒頭で思春期アラームが鳴り響き、指令室は容赦なく破壊され、改築される。新たに登場したシンパイ(不安)、ハズカシ(羞恥)、イイナー(嫉妬・羨望)、ダリィ(倦怠)たちが指令室を占拠し、ヨロコビたち「純」な感情を追い出してしまう。この、否応なく新たな感情たちに支配されてしまう、という流れが、思春期というものを見事に描いている。
ヨロコビたちが育てたライリーの「自分はいい子だ」という自我を、新たにやってきたシンパイがあろうことがゴミ捨て場へと捨ててしまう。シンパイは自分の判断だけで選び出したエピソードで新たなライリーの自我を作り出し、不安感で作り上げられた「自分はダメだ」という自己嫌悪が焦燥感とともにライリーを支配する。
思春期のこのどうしようもなさが本当に見事に表現されている。しかしこの話をどうやって着地させるのだろう。見ながら私はそこが気になっていた。追い出されたヨロコビたちはなんとかして指令室に戻らねばならないし、元の、思春期になる前の「自分はいい子」という純粋な気持ちに戻せばいいという話でもない。どうするのかなと思って見ていたのだが、これ以上ない展開が用意されていた。
ヨロコビたちは忌まわしい記憶が捨てられた意識の果てへたどり着き、光を失いかけている「自分はいい子」というライリーの自我を取り戻す。しかし指令室へ帰る方法がなく、強引に、ゴミの山を爆破し、その山とともにライリーの深層意識へと流れ込む。これが実に見事だ。忘れようとしていた悪しき記憶。叱られた記憶。失敗した記憶。嫌な思いをした記憶。それらを排除して純粋さだけで作られていた自我の泉はシンパイによって不安に塗り固められている。そこへこの悪しき記憶の山とともにヨロコビたちが帰ってくると、これまでのあらゆる経験、良いことも悪いことも、怖かったことも寂しかったことも、全部が一つになる。この作品ではそれぞれの感情に色がついているのだが、あらゆる色の光が一つに集まり、真っ白に輝くという表現がされている。
ヨロコビたちは不安が暴走して、シンパイ本人にすら制御できなくなってしまったライリーの感情を、すべての感情たちで力を合わせて奪還する。マイナスの感情も必要だという前作での結論からさらに一歩進み、嫌な思い出さえも自分を作っている一部であり、要らないものなんて一つもない、という結論に至る。
本作はかように見事な展開でハッピーエンドを迎えるわけだが、ライリーが思春期の複雑な葛藤を超えて前へ進めたのは、追い出された純粋な感情たちが負けずに戻ってきて、新たな感情たちと手を取り合えたからに過ぎない。現実にはこのようなハッピーな展開ではなく、暴走した不安に押しつぶされてしまう人、倦怠に支配されて何もできなくなってしまう人、羨望や嫉妬に支配されて歪んでしまう人などが大勢いる。思春期を迎える前に喜怒哀楽をしっかり磨いておくことが、制御不能に陥らないための秘訣なのかもしれない。

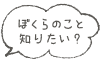





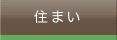
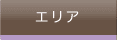
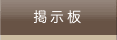



 早乙女カナコの場合は
早乙女カナコの場合は  名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN
名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN  キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド
キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド  ショウタイムセブン
ショウタイムセブン  室町無頼
室町無頼 












