
- ©2025「ショウタイムセブン」製作委員会
報道番組の生放送を舞台に、爆弾テロ犯とのリアルタイムのやり取りを描くスリリングな作品。少々突飛な事件ではあるもののいつ何が起きてもおかしくない緊張感がそこかしこにみなぎっている。爆弾テロ犯が生放送のメディアを狙ってメッセージを流すという、いわゆるエンタメサスペンス作品なのだが、時勢柄、巨大なテレビメディアへの不信感、大義を失った報道の虚無感、タレント化するジャーナリストの無能感など、現在の世情への問題提起としてメッセージ性が強調されて響く。報道メディアとはなんなのか、ジャーナリズムとはなんなのか。その誇りとは。名優阿部寛による主人公の機微の表現が、巨大権力の暴力性とジャーナリズムの本質を暴き出す。
登場する犯罪の実現可能性など、リアリティに関しては「あくまでエンタメ」という出来栄えなのに、それを飛び越えてこの作品が訴える問題提起は強く響く。公開時期が少し違ったら、この作品は単なるサスペンス映画として消費されたのかもしれない。僕らはこれ以上ないタイミングでこの作品を受け取ったと言える。これはヒリつくような「報道」の緊張感を垣間見る、極めて現代的な映画である。(映画ライター・ケン坊)
ケン坊がさらに語る!WEB限定おまけコラム
この記事には映画のネタバレが少々含まれているので、まだ映画を見ていない人はその点をご承知おきの上で読んでください。
テレビ局が報道機関としての誇りを失って久しい。もはや「報道」というものに誰も期待しておらず、その存在意義は無いに等しい。テレビというメディアだけを頼っていると真実などなに一つわからない。本作はそんな現代のテレビメディアに対し、そんなことでいいのかと反省を促すような作品である。報道番組のメインキャスターを降板し、そのテレビ局系のラジオのパーソナリティになっている主人公。彼の元に爆弾テロ犯から電話がかかってくるところから物語が始まる。犯人の主張と主人公の経歴に作品の物語が隠されている。国家権力と巨大資本と報道メディア。この三つが手を結ぶと真実などというものは闇に葬られ、どんな情報操作も可能になるという事案が描かれる。実際問題、現実にも同種のことは既に起きているだろう。報道メディアに中立性など一切なく、スポンサーには頭が上がらないし、コンプライアンスが崩壊しているだけでなく、一般常識も通じない。そのようなメディアと誇りなきジャーナリストへの怒りが、犯人を凶行へと駆り立てる。
本作は「ショウタイムセブン」という架空の報道番組を舞台にしているのだが、この番組の若い女性キャスターが、堕落したテレビを象徴する人物として描かれている。物語のラスト付近で、彼女はあろうことか「たかがテレビですよ」と叫ぶ。たかがテレビ。当のテレビというメディアに出演し、報道番組でキャスターを務める人物が発するこの自己矛盾の極致みたいな言葉。これこそが、この作品で最も描きたかったシーンなのではないかと感じた。番組を作る中核にいる人物さえ、自分たちの作っているものに価値を感じていない。「たかがテレビ」と思っている人たちの作るテレビ番組。そんなものになんの価値があるというのか。この作品は現在のテレビメディアが抱えているこの責任放棄の姿勢を糾弾する作品であるとも言える。
そして極めつけに、この作品を作っている製作陣にも、テレビ局が名を連ねている。絡まりあう自己矛盾が、誇りも責任感もまったくないテレビというメディアを物語っている。

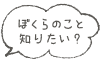





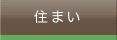
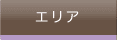
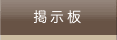



 早乙女カナコの場合は
早乙女カナコの場合は  名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN
名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN  キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド
キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド  室町無頼
室町無頼  ビーキーパー
ビーキーパー 












